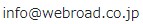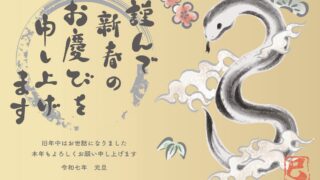今回は自作ブログの品質を底上げするために、公開前に必ず確認してほしい基本項目を整理します。
どれもシンプルですが効果が大きく、読みやすさや検索流入、そして問い合わせや購入への導線づくりに直結します。
記事制作の現場でそのまま使えるよう、実例と手順を交えてまとめました。
1.想定読者がはっきりしているか
最初に確認すべきは想定読者です。
誰に向けて書くのかが曖昧だと、読み手は自分ごと化できず、途中で離脱しがちです。
検索から来た読者は問題解決の答えを探しています。
自分の状況に合うと感じたときにのみ、読み進めてくれます。
たとえば事務所に観葉植物を置きたい人に向けた記事を想定してみます。
- 明るいオフィスに合う種類が知りたい。
- 手間はできるだけ少なくしたい。
- 予算は上限がある。
こうした具体的な条件を想定欄として冒頭で明文化しておくと、構成がブレません。
想定読者メモの例
- 対象 事務所に観葉植物を置きたい人
- 環境 明るめの室内 日光は弱め
- 条件 手入れは楽がよい 予算は上限あり
- 目的 雰囲気を良くして来客印象を高めたい
このメモがあるだけで、本文の取捨選択が容易になります。
2.記事タイトルと本文の整合性が取れているか
タイトルは検索結果で最も目に付く要素です。
主要語が欠けると機会損失が発生します。
観葉植物の選び方を解説するなら、「事務所 観葉植物 選び方」の3語を外さないようにします。
もしタイトルが「事務所を明るくする方法」のように変わってしまうと、観葉植物という主要語が抜けて整合性が崩れます。
良い例と惜しい例
- 良い例 :事務所に最適な観葉植物の選び方
- 良い例 :事務所に置きたい観葉植物おすすめ五選
- 惜しい例 :事務所を明るくする方法
主要語を含めることは検索意図との一致に直結します。
クリックされやすく、内容とのギャップも生まれにくくなります。
3.検索キーワードへの答えになっているか
読者は疑問に対する具体的な答えを求めています。
観葉植物の選び方であれば、広さの考え方、水やり頻度が少なくて済む種類、蛍光灯だけでも育ちやすい種類、サイズが変わりにくい種類、予算に優しいが見栄えする種類、緑以外の色味を楽しめる種類など、プロの視点から選定基準を列挙し、選び方の道筋を提示します。
答えの厚みが増して一記事が大きくなり過ぎたら、軸で分割するのがおすすめです。
大きさ別、価格帯別、手間の少なさ別などで独立記事にし、相互リンクで束ねると、個別の検索意図にも高精度で応えられます。
| 分割軸 | 例 | 読者メリット |
|---|---|---|
| 大きさ別 | 小型 中型 大型の配置と注意点 | 設置スペースと動線を計画しやすい |
| 価格帯別 | 予算内で見栄えを最大化するコツ | 購入判断が迅速になる |
| 手間別 | 水やり頻度と育てやすさの目安 | 維持コストの見通しが立つ |
検索語に対して一問一答で応える段落を意識すると、読み手が迷いません。

4.段落設計と改行が読みやすさに配慮されているか
文章が途切れなく続くと、画面では読み進めにくくなります。
意味のまとまりごとに段落を作り、段落間は1行空けると視線の移動が楽になります。
3行から5行を目安に段落を切り、見出し直下には結論の要約を2行ほど置くと、読みやすさがさらに高まります。
段落づくりのコツ
- 1段落に1要点を徹底する
- 見出し直下に結論の要約を置く
- 箇条書きで条件を並べると可読性が上がる
- 同一主語と同一時制で並べてリズムを出す
改行の位置は音読して、違和感が無いかを指標に調整すると、自然なリズムが生まれます。
5.画像や図表で視線を休ませているか
文字の連続は負荷が高く、途中離脱の原因になります。
本文の意味が変わらない範囲で、図版やイラスト、簡易な比較表を挿入しましょう。
段落四つに一つの目安でビジュアルを挟むと、読了率が上がります。
画像は本文の要点を補助する役割に徹し、装飾だけの挿入は避けた方がいいでしょう。
画像選定のポイント
- 本文の主張を1枚で補足できるものを選ぶ
- 情報が古くならない汎用的な図版を用意する
- 代替テキストを短く具体的に記す
- ファイル名とキャプションに主要語を含める
画像の有無は読み手の疲労感に直結します。適切な間隔で視線の踊り場を設けましょう。
6.第三者の目で読みやすさと伝わりやすさを検証しているか
自分では分かりやすいと思っていても、読み手にはそう感じないことがあります。
利害関係の無い第三者に読んでもらい、率直な意見をもらいましょう。
- 誰に向けて書いているのか。
- 結論はどこにあるのか。
- 用語は過不足なく説明しているか。
- 読後に何をすればよいか。
これらが一読で伝わっているかを確認します。
第三者チェックリスト
- 対象読者が冒頭で明示されている
- タイトルと本文の主旨が一致している
- 検索語への答えが段落単位で用意されている
- 段落と見出しで迷子にならない
- 次の行動への導線が明確である
社内で依頼する際は遠慮が生まれがちです。
外部の知人や厳しめに指摘できる相手に頼むと、改善点が明確になります。
実装チェック 手順とテンプレート
ここからは公開前の実装チェックの流れです。記事ごとにテンプレート化して使い回すと、品質のバラつきが減ります。
| 1.想定読者 | 誰のどの状況に向けた記事かを二行以内で記述 |
| 2.タイトル主要語 | 対象 課題 解決語の三点を含める |
| 3.要約 | 見出し直下に結論の短文を配置 |
| 4.段落設計 | 三行から五行で段落を区切り一行空ける |
| 5.図版 | 段落四つに一つを目安に挿入 代替テキスト必須 |
| 6.導線 | 関連 設定例 価格 問い合わせへのリンクを配置 |
| 7.校正 | 誤字脱字 用語統一 数字の桁区切りを確認 例 1,000 |
| 8.第三者レビュー | 利害の無い読者に読了印象と詰まり箇所を確認 |
記事を厚くするための具体例づくり
先の例でいうと、(観葉植物の)選び方という抽象を具体に落とし込むと、記事の満足度が跳ね上がります。
観葉植物なら、価格別の候補一覧、水やり頻度ごとの候補、設置場所別の候補一覧、鉢と受け皿のサイズ表、導入後の手入れなどを小見出しで積み重ねます。
数字は可能な限り具体にし、1,000や5,000など桁を区切って視認性を高めましょう。
また、本文中の疑問になる可能性のあるものを拾い、後半に小さなよくある質問&回答集を用意しておくと、離脱前の疑問解消に役立ちます。
長期運用を見据えた記事の分割と連結
大枠の記事で検索意図を網羅しつつ、後日アクセスが集まる項目を取り出して、独立記事にします。
親記事から子記事へ内部リンクを張り、子記事から親記事に戻るリンクも設置します。
これによりサイト内回遊が生まれ、関連テーマ全体の評価が上がります。
更新履歴を明記し、追補を積み上げていく姿勢を示すと、再訪率が向上します。
読みやすさの微調整で仕上げる
- 漢字とひらがなのバランスを整える
- 接続詞の連発を避ける
- 連文節の修飾を一段減らす
- 主語と述語の距離を縮める
- 専門用語には短い言い換えを付ける
最終段階のこの五点だけで体感の読みやすさが大きく改善します。
〈まとめ〉まずは五項目を確実に満たす
- 想定読者の明確化。
- タイトルと本文の整合。
- 検索語への具体的な答え。
- 段落と改行の設計。
- 画像や図表で視線の踊り場をつくる。
この五項目を満たすだけで、記事の価値は大きく跳ね上がります。
仕上げに第三者の目で確認し、詰まり箇所を1つずつ解消しましょう。
今日整えた1本が、明日の信頼と成果につながります。
投稿者プロフィール

- 2004年頃の会社員時代からブログ作成を始める。ブログ作成が楽しくなり、そのまま趣味が高じて2006年にホームページ制作で起業、2008年に株式会社ウェブロードを設立。現在は、個人・中小事業者のWordPressサイト制作・改善を中心に、Web業界18年の知識と経験を生かして、大型案件のWebディレクターとしても活動中。 プロフィールはこちら
最新の投稿
 お知らせ2025年10月21日自作ブログの記事で必ずチェックしてほしい項目
お知らせ2025年10月21日自作ブログの記事で必ずチェックしてほしい項目 メルマガバックナンバー2025年10月17日AIと検索に評価される記事の書き方
メルマガバックナンバー2025年10月17日AIと検索に評価される記事の書き方 コンテンツ制作2025年10月15日広告を出しても応募が来ない理由と採用ページに惹きつける設計
コンテンツ制作2025年10月15日広告を出しても応募が来ない理由と採用ページに惹きつける設計 お知らせ2025年10月13日ホームページを顧客自動選択マシンに進化させる方法
お知らせ2025年10月13日ホームページを顧客自動選択マシンに進化させる方法
お問合せフォームはこちら
弊社サービスをご検討いただきありがとうございます。
こちらのカテゴリ内のご質問と回答で解決できない場合は、ぜひ下記フォームよりお問い合わせください。ご相談・お見積りのご依頼は無料です。
お申込前のお打ち合わせはメール/お電話/GoogleMeet等オンラインでもご対応可能です。全国からお問い合わせを受付けています。 翌営業日を過ぎても弊社からの連絡がない場合はメールが届いていませんので、大変お手数をお掛けしますが、下記メールアドレスにご連絡ください。
翌営業日を過ぎても弊社からの連絡がない場合はメールが届いていませんので、大変お手数をお掛けしますが、下記メールアドレスにご連絡ください。